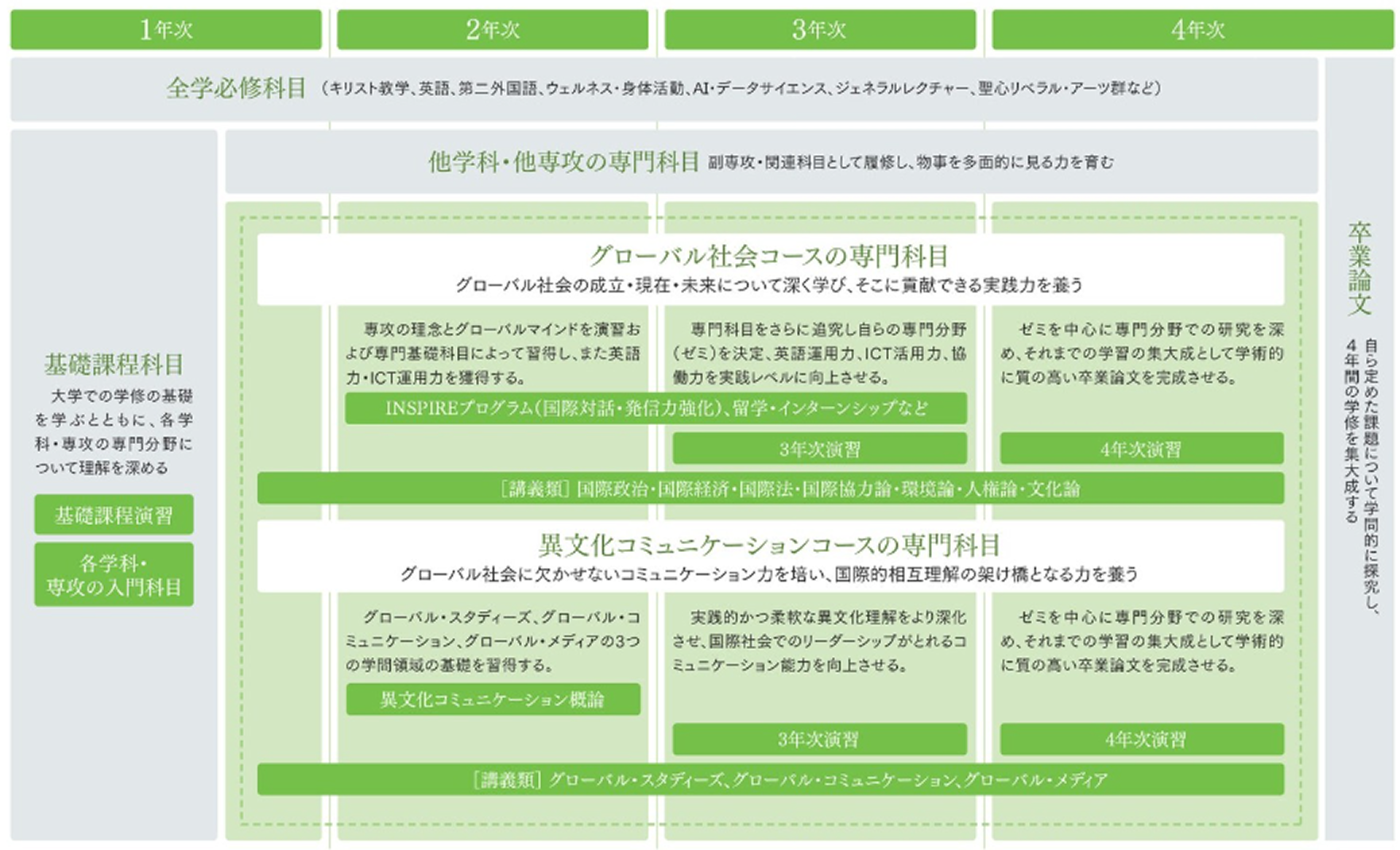グローバル社会コース
グローバル社会の成立・現在・未来について深く学び、
そこに貢献できる実践力を養う
そこに貢献できる実践力を養う
国際政治、国際経済、国際法、国際文化協力、地球環境分野の最新の専門知識に裏付けられたグローバルな視野に加え、発信力・協働力・英語運用力・ICT活用力などのスキルを養います。海外体験や各自の個性的なプロジェクトを通して知識を実践に移し、思考力と深いコミュニケーション力で世界の諸課題を解決していく人間を育成します。
Keywords
#国際政治 #安全保障 #国際経済 #知識経済・デジタル社会 #グローバリゼーション #国際法 #⼈権保障 #多⽂化共⽣ #⽂化多様性 #世界遺産 #国際機関 #国際協⼒ #SDGs #開発援助 #地球環境 #市民社会 #ESG #アクティブラーニング

専門科目
専任教員紹介

- ①専門、研究テーマ
- 国際政治学、外交・安全保障論
- ②①に興味を抱いたきっかけ
- 子供の頃に、戦争ってみんなが嫌がるはずなのになぜ起こるんだろう、と思ったのが一番のきっかけですね。あとは、単純に、知らないことを知るワクワクが大好きでした。(この気持ちは現在進行形。)
- ③ゼミについて(授業内容など)
- 国際政治の現状と学問的アプローチはもちろんですが、それぞれが興味のある問題を見極め、それをどうやって追究し、またうまく人に伝えられるか、を強く意識しています。そして何よりも(辛いところもあるけれど)すごく楽しい!という感覚を一番大切にしています。
- ④学生時代の思い出
- 大学内には最低限しかいませんでした。いろんな人と会い、旅をし、これから何をすべきなのか、ずっと考えていました。
- ⑤学生へのメッセージ
- 大学でやるべきなのは、自分の常識を深く深く疑ってみること、偶然を大事にする癖をつけること、一人で生きる準備をすること、ですね。

- ①専門、研究テーマ
- 専門:国際経済学 国際政治経済学
研究テーマ:
・21世紀の地球村(グローバル・ヴィレッジ)での共生と協力
・人々が自発的に集まって協力するメカニズムの解明(コレクティヴ・アクション)
・グローバル社会での国際公共財の提供問題
・ICTやAIが作り出していく新しい知識経済のしくみ
・ポスト資本主義はどのような経済制度になるのか - ②①に興味を抱いたきっかけ
- 人々なぜ争うのだろう、世界はどうして戦争をするのだろうと、国際関係と平和の問題を深く考えていくと、戦争や紛争の根底には常に経済の問題があることに気づきました。権力者にとっても普通の国民にとっても、国際経済の問題を抜きにして世界平和を考えることはできないと思ったのが、国際経済学を志したきっかけです。
- ③ゼミについて(授業内容など)
- 3年生では国際経済の基礎を輪読などで学んだ後、秋に向けてテーマを選び共同研究を開始します。慶應、関西学院大学など、関東・関西の大学とのインターゼミナール行い、オリジナルの論文を発表し、ディスカッションをするためです。英語論文になることも多いです。中間報告を夏合宿と聖心祭で行います。研究を通じて思考力や論理力がつくと同時に、他大学に仲間もできて実践力や協働力、発信力がつきます。その後4年にかけて、社会の難問をビジネスで解決する「ソーシャル・ビジネス」の企画案をグループで練り、聖心祭で発表します。学習の集大成として、卒業論文に全力で取り組むことは言うまでもありません。
- ④学生時代の思い出
- 当時私は好奇心の塊で、文学やいろいろな分野の本を読み、旅行をし、数か国の語学を学び、友と大いに語り合い、緒方貞子先生はじめ他大学の授業も聴講し、スポーツをし、名画を観、そしてたくさん考えていました。もやもやとした将来への不安の中で、最大の悩みは自分の将来の夢をひとつの職業名で示すことができなかったことでした。自分には何ができるのだろう?自分の核は何だろうと迷い、笑い、青春をしていたように思います。霧の中にいたけれど、その問いをあきらめなかったな、という感覚だけは今もあります。
- ⑤学生へのメッセージ
- これから世界は、大きな転換期・変動期に入ると思います。自分の選択する道が、自分にとっても世の中にとっても悔いのないものにするために、大きく視野を開いて、世界を判断する軸や芯を自分の中にしっかりと形成してほしいと思います。

- ①専門、研究テーマ
- 文化遺産学、文化政策、国際文化協力
- ②①に興味を抱いたきっかけ
- 10代の頃に「戦争は心の中に生まれるものだからそれを防ぐためには心の中に平和の砦を築く」ことを理念に掲げる国連機関(ユネスコ)での勤務を目指すようになりました。その夢かない、20代半ばから30代半ばまでユネスコのパリ本部で、世界遺産関連アドヴォカシーをおこなう一担当官として勤務。アジアやアフリカのたくさんの「現場」に立って肌で感じ、国際協力の理想と現実の狭間で、より多くの人にとっての幸せとは何かをいつも考えていました。職場の日常自体も、きわめて文化多様性に富んでいました。大学院時代の研究をベースに多国間協力の仕事を通して得た知見、それらを総合して深めた博士学位論文のための研究が、現在にまで至る研究アプローチの基礎となっています。
- ③ゼミについて(授業内容など)
- 自然・文化遺産を保全しつつ持続可能な発展を目指す世界遺産マネジメントの五大陸26事例を取り上げた英語文献を各自が一章ずつ担当解析します。担当者のプレゼンと議題提起を受けて毎回必ず全員が意見を返し、議論は発展していきます。ゼミ生はバランスのとれた世界観を構築し、実践的な視点でグローバルとローカルの間の協力課題を考える姿勢を身につけていきます。卒論は、一生をかけて考えていきたい問いにひとりひとりが深く取り組めるように、まずはオリジナルな「自分らしいテーマ探し」方法から入り、進めていきます。
- ④学生時代の思い出
- 体育会のテニス部に所属していました。体力的限界を覚えながらハードな練習や真剣勝負を経験し、縁の下の力持ち的な役割分担の数々をこなす喜びも知りました。しかし、二年やったところで三年次から留学するため辞めてしまいました。留学は充実していて楽しく、その後へ道が開けるきっかけにもなりましたが、現時点で鮮烈に蘇ってくる学部時代の思い出といえばテニス部の仲間達との時間です。泣き、笑い転げ、悔しがる、が全て本気で、輝いていて、最高でした。
- ⑤学生へのメッセージ
- 時にはまわり道と感じられるような経験も大切に丁寧に乗り越えて、人間としての幅や引き出しを豊かに持った人になっていただきたいなぁと思います。大学は知識を得るだけの場所ではなく、学生時代は学内外で出会うさまざまな人から学び、自分らしいhow to liveの姿勢を身につけるチャンスだと思います。「輪郭」や「スタイル」といった個性をもって、それを発揮し周りを照らすことのできる人となって下さい!

- ①専門、研究テーマ
- 国際法学、特に国際人権法
外国籍住民やマイノリティを含んだ実質的平等な人権保障のあり方について、国連の人権保障制度、ヨーロッパの地域的人権保障制度、日本における人権条約の国内適用を中心に研究しています。 - ②①に興味を抱いたきっかけ
- ちょうど中東欧諸国(ポーランド、チェコ、ハンガリーなど)がEUに加盟した直後の時期に学部時代を過ごし、この地域の民族問題に興味を持ちました。同じ時期、日本では「多文化共生社会」をキーワードに外国籍住民の社会生活への関心が高まっており、さらに、留学生が多い大学だったこともあり、マイノリティに対する人権保障という問題に興味を持つようになりました。大学では国際関係論や教育行政にも関心を持ったのですが、国を越えた人権保障を目指す国際人権法という分野を専攻するようになりました。
- ③ゼミについて(授業内容など)
- まずは、受講生の皆さんに広い意味での「人権問題」に興味を持って頂き、さらに、国際法・人権法上の論点との結び付けて考えられるようになることを目指します。分野の性格上、裁判の判決や国連をはじめとする国際機関で採択された文書を読むことが多くなりますが、初めのうちは翻訳・解説があるもの等、読みやすいものを取り上げるつもりです。また、最初から法律論に深入りすることよりも、受講生一人ひとりの関心事を「人権」と結び付けてとらえる視点を養うことを重視します。
- ④学生時代の思い出
- 真面目な回答としては、上記2で述べた通り、興味関心が広く、国際法や国際政治等の社会科学系の科目のほか、言語学や東欧文学等の科目もとっていました。その合間で、住み始めたばかりの東京の名所を見に行ったり、思い付きで旅行に出かけたりと、マイペースな生活をしていました。学生時代(特に学部生のとき)の経験の中には、今に直接つながっていることとそうでないことがありますが、今でも「学生時代」として思い出すのは、それなりに忙しいながら自分のペースで暮らしていた学部生のときのことです。
- ⑤学生へのメッセージ
- 大学によって用意された授業や課外活動などの「守られた」環境だけに身を置かず、時には自分にとって快適ではない場にも出向いて、自分にとって「当たり前」のこととは違う視点を持ってください。そして、世の中の仕組みや出来事に対して、「何となくおかしい」と思うことを言語化し、他人に伝えてみてください。自分とは合わない考えを持っている人に接することもあると思いますが、そのような人を拒絶するのではなく、(最終的に同意するかどうかは別として)相手がそのように考え、自分がそれを受け入れられないのはなぜなのかを理解しようとすることを大切にして頂きたいと思います。

- ①専門、研究テーマ
- 専門は、環境学、森林保全政策、国際環境経済学、環境金融、環境問題への対応策の検討など。現在の研究テーマとしては、気候変動や生物多様性保全を含めた様々な環境問題の中でも、特に森林保全のために必要な企業や金融機関、消費者、政府などの役割を研究しています。
- ②①に興味を抱いたきっかけ
- 開発問題に興味があったときに、国際金融機関が支援して途上国で行われている植林活動が、現地の環境や人権に悪影響を及ぼす事例について、NGOの国際会議に参加して学んだことがきっかけです。森林を増やすということで良いイメージがある植林活動ですが、植林地造成のために天然林が伐採されたり、元々住んでいた地域住民や先住民族の土地が奪われたり、色々と悪影響を及ぼす事例を学ぶ中で、森林問題に興味を持つようになりました。
- ③ゼミについて(授業内容など)
- 環境問題とその問題への企業や政府等の対応策についてゼミ生とともに探究しています。基本的には、ゼミ生が興味関心を持っている環境問題について掘り下げていくことにしています。3年の前期は、輪読を行うことで基本的な内容を学び、問い、考える機会を作ります。後期には、ゼミ全体で取り組めるテーマについて調べるとともに、個々人の取り組むテーマについても探索を始めて、学び合う機会として4年での卒論の執筆につなげていく予定です。
- ④学生時代の思い出
- 今思うと、学生時代は、いろいろと思い悩んでいました。悩んでいたので、答えを見つけようと様々な分野の本を読んだりしていました。元々、本を読むのは全く苦手だったのですが、おかげで、関心がある分野のものは読めるようになりました。様々な分野の学問について探索することで自分探しをしていたのかもしれません。また色々と社会問題にも関心があったので、いろんな活動に首を突っ込んだりもしていました。そこからNGOにも関わり始めました。
- ⑤学生へのメッセージ
- 何か自分自身が興味や関心を持っているもの、面白いと思っているものについて、少し深く調べてみたり、考えてみたり、活動してみたりしてみて下さい。そこから自分の得意分野や専門分野や、やってみたことも見つかってくると思います。すでに見つけている人は、その分野をどんどん深掘りしてみて下さい。どんなことでもいいので、自分が興味・関心を持てることを見つけて、それに取り組んでみてください。そこから新たな未知の自分に出会うことができるかもしれません。
卒業論文
国際政治(指導教員:坪内淳)
- 米中貿易戦争から考える保護貿易の原因―恐怖という感情が国際政治に与える影響―
- 米中対立の時代における日ASEAN外交の意義―自由で開かれたインド太平洋(FOIP)推進の視点から―
- アフガニスタンの女性教育支援ータリバン暫定政権下における国際社会の役割ー
- 多民族国家インドネシアにおける民主化―民主主義の定着に寄与する5条件の相互関係と国家性―
- フェミニスト国際関係論が日本の男女不平等問題に与える影響 ―ジェンダーを巡る理論と実践―
- 日韓対立感情と埋まらない溝―韓国の歴史教育が日韓外交に与える影響―
- 日本における外国人留学生の就労問題-企業と大学による多文化共生への貢献-
国際経済(指導教員:古川純子)
- なぜ人は結婚するのかー現代における結婚のメリットを考えるー
- 巨大IT企業への課税のあり方
- 日本の所得低迷と付加価値創出の鈍化ー産業高度化に伴う日本経済の停滞を考えるー
- 観光地運営のあり方に関する考察ー京都のオーバーツーリズムにおける課題解決に向けてー
- 日本半導体産業復活の鍵 ―世界的ファウンドリと築く新たなサプライチェーンの形―
- 日本における宇宙産業の展望ー宇宙開発利用で解決すべき課題とその解決策ー
- ナッジ理論賛成率の国際比較ー日本の課題とナッジ理論のその先ー
国際文化協力(指導教員:岡橋純子)
- 文化は国境をどう越えるかー朝鮮半島の2つの無形文化遺産を事例としてー
- イタリアの保全型都市計画に関する一考察
- 表現の自由とは何か―ファッションやアートを通してみる文化の模倣と盗用―
- アメリカ音楽の多様性と社会性 ―ブラックミュージックは文化の分断か、融合か―
- カナダの多文化主義におけるケベコワアイデンティティの位置づけ
- ケルン大聖堂に現れる象徴性
国際人権論(指導教員:佐々木亮)
- 中国のウイグル族に対する人権侵害と国際社会
- 外国人労働者の人権保護〜日本における短期的労働者に焦点を当てて〜
- 国際人権法における精神障害者の権利―医療保護か強制入院か―
国際環境論(指導教員:川上豊幸)
- 廃プラ輸出入規制は環境のため、人のために良い影響を与えているのか
- 「自然の権利」の実現可能性―訴訟事例の国際比較と環境倫理の視点を交えて―
- 衣類の大量廃棄構造改善により実現する循環型のファッション産業とは
- 日本における持続的な野生動物管理の課題と可能性について―海外と国内の比較から―
- 自然に対する関心の差を生む学校教育の差はどこにあるのか
- 漂流・散乱するペットボトルごみをなくすために、日本においてデポジット制度は実現可能なのかーデポジット政策を国際比較してー
- 衣類の廃棄を減らすために日本はどうすべきか
国際政治(指導教員:坪内淳)
- ハイブリッド戦争−サイバー空間に広がる戦争形態の変化−
- 軍事にジェンダーの平等と多様性は必要か? ー兵役問題を中心に考えるー
- 宗教はテロリズムの動機となり得るのか ―宗教思想及び、社会的要因に着目して―
- 覇権国の変遷と国際連合の機能不全
- アメリカとキューバの国交正常化―政治・外交・経済ファクターから見る背景と展望―
- 航空分野の脱炭素化へのあゆみー持続可能な航空燃料(SAF)が担う役割と日本における導入の将来性ー
- 移民と日本社会 入管法改正の是非
- アメリカ社会で政治争点となった女性の中絶権利 ~なぜ中絶論争は激化するのか~
- 日本での「主体的・対話的な学び」の実現性〜学校教育の現場で主権者を育てるためには〜
国際経済(指導教員:古川純子)
- 環境と経済の両立は可能か―企業の環境への取り組みと収益性の関係―
- ソーシャルビジネスの成功要因は何か
- 労働組合はアメリカの格差を是正できるか
- 問題だらけの日本の”負”動産 ー国際比較からみる空き家問題の構造的課題ー
- 日本がEVシフトに出遅れた要因分析 −中国・韓国メーカーとの戦略比較−
- 日本の二国間ODAの変遷と経済効果 ―ODA改革に対する検討―
- レアアースを巡る経済力の国際的パワーシフト ―永久磁石の中国依存脱却は可能か―
- 日本におけるバレエ人口の拡大と芸術的卓越性のジレンマ ―プレイヤーの労働条件とバレエ団の経営を安定させるには何が必要か―
- 親子関係が子どもの意思決定に与える影響
- 有田焼の経済的自立と発展ー伝統産業の普遍的課題ー
国際文化協力(指導教員:岡橋純子)
- ショパンの楽譜、「世界の記憶」への登録意義 −音楽がポーランドのソフトパワーに繋がるのか−
- 難民の受容と教育に関する考察―トルコのシリア難民を例として―
- バレエ作品『白鳥の湖』の国際的発展と普遍性をめぐる考察
- 農業景観に関する国際的議論と日本への影響
国際人権論(指導教員:佐々木亮)
- 国教制度と国際人権法における信教の自由の保障 ―イギリスと英国国教会の関係からの考察―
- 方言話者の権利保障と日本の言語の多様性
- 外国人の子どもの教育についての権利―日本における不就学問題―
- ビジネスにおける人権尊重に向けて ―日本企業の人権デューディリジェンスの実践から―
- 知的財産の国際保護が医薬品アクセスにもたらす影響―医薬品の普及状況から見る国際人権法と国際経済論の交わり―
- 改正少年法から見る「特定少年」の人権と責任
- 日本における障害者権利条約の実施ー総括所見で要請された自立生活に関する考察ー
国際政治(指導教員:坪内淳)
- 人道的介入が正統性を持つために―保護する責任論から見る人道的介入の課題―
- 「芸術文化」と人々の生活
- 対米関係から見る中南米の麻薬ビジネス―コロンビアの事例から推察するメキシコの麻薬ビジネスの今後―
- 日本企業のインドBOPビジネスにおけるジュガード・イノベーションの必要性
- 核のNFU宣言は核軍縮への第一歩となるのか―核抑止論からの考察―
- 日本とドイツの政治教育について
- 企業のLGBTマーケティングによる経済効果とLGBT環境変化の可能性
- アメリカの銃規制は現実的なのか?
- 韓国の広報文化外交が韓国国民のナショナルアイデンティティにどのような意味を付与するのか―韓国の広報文化外交の今後と課題―
国際経済(指導教員:古川純子)
- 日本の膨大な針葉樹人工林の放置問題は森林の誘導によって解決できるか
- 日本の貧困格差―日本の社会保障制度の脆弱性とフレキシュリティの可能性―
- 日本のジェンダー平等 ー都道府県別ジェンダーギャップ指数分析ー
- 日本の労働力人口不足の2つの解決策について―外国人労働者の受け入れと A I の運用―
- 日本の働き方改革に対する量的評価と今後の働き方改革におけるテレワークの重要性
- ショールーミング行動へ有効な対策とは―大手家電量販店4社の事例―
- 金融機関における自己資本の増強が実体経済に与える影響 ―資産価格バブルを生み出す非伝統的金融緩和政策は適切か―
- なぜ日本企業のデジタルトランスフォーメーションは遅れているのか
- 世界の変動とアメリカの衰退
- 楽天の海外展開失敗要因 -楽天・アマゾン・アリババのビジネスモデル比較から分析-
国際文化協力(指導教員:岡橋純子)
- 都市空間の在り方を考える―建築家ヤン・ゲールの「人中心の街づくり」に学ぶプレイスメイキング―
- サードプレイスの創出に関する一考察―「居場所」の意義とは何か―
- インバウンド・ツーリズムによるスキー観光の変容―持続可能な観光資源とは何か―白馬村の事例を通して
- 日本のフードツーリズムに関する一考察ーフードトレイルに見出す持続可能性とはー
- ジェンダー主流化に関する一考察―カンボジアとインドにおける開発プロジェクトを例に―
- ウガンダにおける難民教育の課題―援助機関の連携とNGOの位置づけ―
- ベトナム諸都市の変遷と都市開発の課題
- 貧困問題におけるコミュニティ開発の有効性―フィリピンの開発プロジェクトを例に―
- 渋谷らしさの移り変わり―再開発から見える街の個性とアイデンティティ―
国際人権論(指導教員:佐々木亮)
- 日本におけるインクルーシブ教育―人権条約から見る障害のある子どもの教育についての権利―
- 国際安全保障が女性に与える影響
- 自動車の自動運転から考える A I の活用と課題―人工知能の可能性と人権問題、社会課題時代に合った人権の守り方―
- 雇用から考える日本の男女格差における課題
- 水道事業民営化と水に対する人権―国際経済法と国際人権法の対立―
- 入管収容制度から見る日本における難民認定の問題点
- 日本における緊急避妊薬薬局販売の可能性